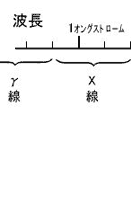
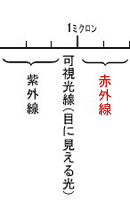
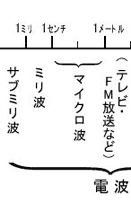
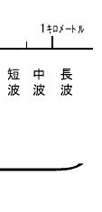
(1オングストローム:1000万分の1ミリ、1ミクロン:1000分の1ミリ)
赤外線は赤色の光(可視光線)よりも波長が長く、エネルギーの低い電磁波です。波長は約0.7ミクロン(1ミクロン=1000分の1ミリ)?0.1ミリ程度までです。電気通信では波長0.1ミリ以下の電磁波は赤外線として扱われますが、天文学ではこの波長域まで含めてサブミリ波(電波)と呼ぶこともあります。
赤外線は目には見えません。もっともよく知られているのは、こたつの出す赤外線ではないでしょうか? 赤外線は温度の高い物体から出て、熱作用が強いという性質があります。
天体には赤外線を出すものが多く、赤外線による観測技術が発展すれば、多くの発見があると言われています。これまでに打ち上げられた赤外線天文衛星は、日本の「あかり」、「IRTS」、NASAの「IRAS」、ESAの「ISO」などがあり、数々の赤外線天体を発見してきました。
赤外線観測の成果としては、原始星の発見、銀河系中心の構造に関する発見などが挙げられます。
宇宙科学研究機構では、「SPICA」など、更に大型の赤外線望遠鏡を打ち上げる計画を進めています。
関連リンク ※別ウィンドウが開きます。
赤外線天体物理学グループ (ISAS)
赤外線天文衛星「あかり」 (ISAS)
「IRTS」 (ISAS)
「SPICA」 (ISAS)
大気球観測:遠赤外線で見た銀河中心 (ISAS)
「IRAS」 [英語]
「ISO」 [英語]